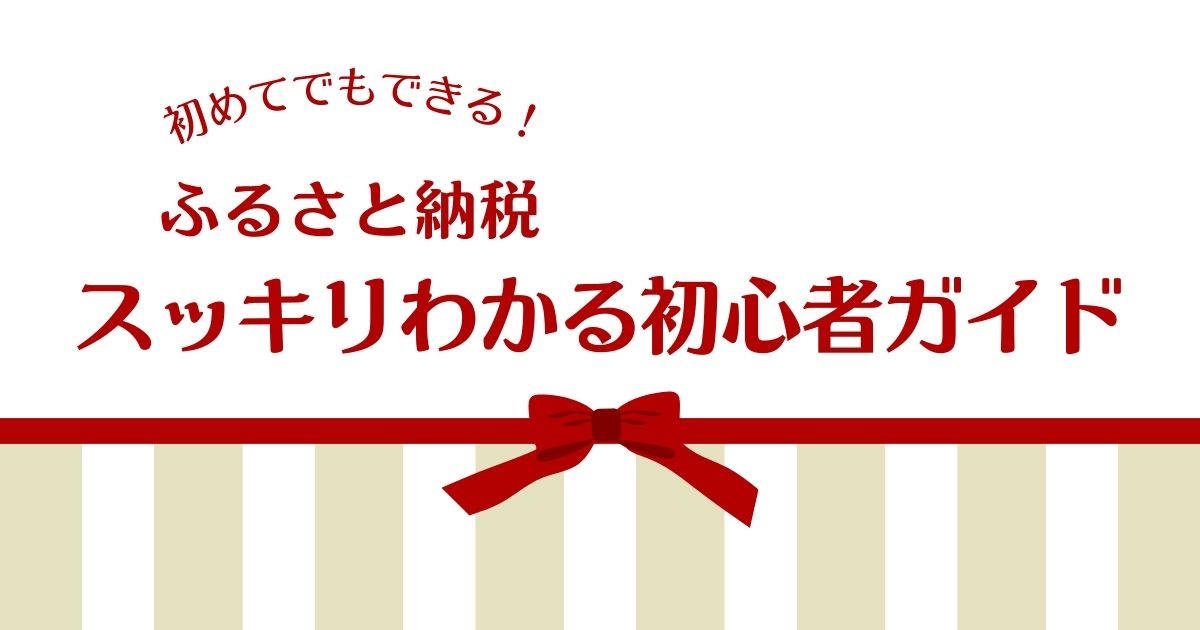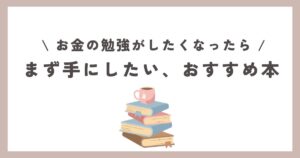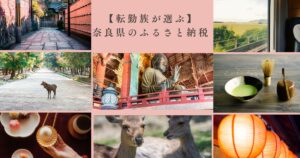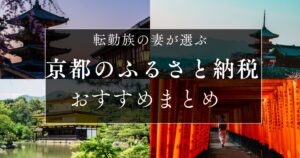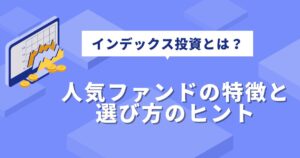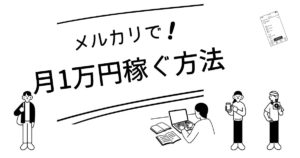教育費が高い…少しでも家計の負担を減らせる制度があれば利用したいな。
「ふるさと納税」ってよく聞くけど、実際どうなのかな?



ふるさと納税には、「年間数万円の”隠れ家計サポート”」のような要素があるので、教育費がかかる家庭こそ、ふるさと納税を活用する価値が高いです。
今回は、そもそもふるさと納税とはどんな制度なのか、何がお得なのかを、FPの視点からわかりやすく解説します!
この記事を読んでわかること
ふるさと納税とは?基本の仕組み
ものすごく簡単にまとめると、
1年間に稼いだお金には所得税がかかります。
また、住民税は、所得税の情報をもとに算出されます。
ふるさと納税は、寄附した金額から2,000円を差し引いた分が、翌年の所得税・住民税から控除される仕組みです。
ふるさと納税の誤解あるあると実際のしくみ
| よくある誤解 | 実際は… |
|---|---|
| 課税所得が減る | 税額から直接控除される |
| 全額戻ってくる | 2,000円は自己負担 |
| 所得税だけが減る | 住民税も含めて控除される |
| 控除=節税 | 節税ではなく「税金の使い道を選べる制度」 |
※ふるさと納税は「節税」ではなく「寄附金控除」という制度です。 寄附した分が税金から差し引かれることで、実質的にお得になる仕組みですが、 本質は“税金の使い道を自分で選べる制度”という点にあります。
ふるさと納税の基本ステップ
ふるさと納税の基本ステップはこのような流れです。
ポータルサイトから寄付ができます。また、各自治体のホームページや、自治体の直営サイトがある場合もあります。
返礼品を選ぶのは楽しいですね!
ワンストップ特例なら、確定申告しなくてもいい!
税金が控除される!
例えば10万円のふるさと納税を行った場合、自己負担2,000円を除いた9万8,000円が税金から控除されます。
日々の生活で9.8万円分もお金を浮かそうとすると、いったい何をどのくらい削ればいいのでしょう?そう考えると、いろんな自治体を知ったり、返礼品を楽しく選んだりするだけで、しかも2000円のみの自己負担で、こんなにお得な制度、見逃すわけにはいきません。
制度を知って、家計の味方にするチャンスです。



私が実際に利用したことのあるふるさと納税ポータルサイトはこんな感じです▼
| 公式サイト | 私の感想 |
|---|---|
| ・サイトが使いやすい。見やすい。 ・自治体数や返礼品数も多いので楽しい 👉手順解説記事はこちら | |
| Amazonふるさと納税 | ・Amazonユーザーは非常に操作が楽。 ・まるでAmazonでお買い物をしている感覚で寄付ができる |
| 楽天ふるさと納税 | ・楽天ユーザーは非常に使いやすい。 ・楽天でお買い物をする感覚で寄付ができるので簡単。 👉手順解説記事はこちら |
| 「ふるなび」 | ・家電製品の返礼品が多い。パソコン、炊飯器、洗濯機など、珍しいものが掲載されているので、見ていて楽しい。 |
▼実際にふるさと納税を始めてみたい方へ
・「ふるさとチョイス」での具体的な手順は👉こちらの記事で紹介しています
・「楽天ふるさと納税」での具体的な手順は👉こちらの記事で紹介しています
【FP解説】教育費がかかる家庭こそふるさと納税を活用すべき3つの理由
ふるさと納税がお得ということがわかったところで、では、教育費がかかる家庭にどのようなメリットがあるのか、教育費がかかる家庭こそふるさと納税を活用すべき理由3つをここであげてみたいと思います。
理由①:実質的な節約につながる
- ふるさと納税は「自己負担2,000円」で、実質的に“買い物”ができる制度
- 教育費で家計が圧迫されている家庭にとって、日用品・食料品・生活必需品を返礼品でまかなえるのは大きなメリット
- 「出費を抑える」というより、“支出の一部を寄附で置き換える”感覚
理由②:家計の見直しのきっかけになる
- ふるさと納税をするには「控除上限額」を知る必要がある
- その過程で「我が家の年収・所得・税金ってどうなってる?」と家計の棚卸しができる
- 教育費がかかる時期こそ、家計全体を見直すチャンス
理由③:将来の教育費に備える“意識づけ”になる
- 「今使うお金」と「将来のために残すお金」を意識するきっかけになる
- ふるさと納税は“節税”ではなく“税金の使い方を選ぶ制度”だから、お金の価値観を整える練習にもなる
家計の見直しのきっかけになったり、マインドを変えられるということだけでも、良い変化になると思います。
また、返礼品を選ぶ楽しさがありながら、住民税と所得税の負担を軽減できるのも魅力です。
我が家のふるさと納税歴とリアルな使い方、おすすめ返礼品
実際に、我が家でもふるさと納税を活用して家計を助けてもらっています。 ここからは、我が家のふるさと納税歴と、リアルな使い方とおすすめ返礼品についてご紹介します。
我が家のふるさと納税歴
私がふるさと納税を始めたのは、2013年のことです。 制度ができた当初から「どうやらお得らしい」という話は聞いていたものの、 実際にどうやればいいのか、何がどうなっているのかがまったくわからず、 こわくて手が出せずにいました。
それでもようやく2013年にデビューしてからは、毎年欠かさずふるさと納税を続けています。
最初は不安だったけど、やってみたら意外と簡単で、今では毎年の楽しみになっています。
私のおすすめ返礼品(教育費のかかる家庭向き)と地域選び
ふるさと納税歴10年以上の私の返礼品選びの順番は、まず地域を厳選してから、商品を選ぶ、というようにしています。
そして、肝心の地域選びですが、親族がいる地域や、転勤族として数年暮らしたことのある地域など、なにかしらの縁があるところを中心に選ぶことが多いです。(全然親族もいないし、暮らしたこともない地域でも、ファンとして毎年ふるさと納税している地域・返礼品も多数あります)
総務省「ふるさと納税ポータルサイト」には、ふるさと納税の理念のうちの1つとして、このような一文があります。
「生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。
それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。」
この理念に則り・・と強く意識せずとも、あ~おじいちゃんおばあちゃんがいた地域、懐かしい。あそこのあれおいしかったな、返礼品はあれにしよう。あの地域、頑張ってほしい。という気持ちで、ほんのわずかですが応援団として寄付しているつもりです。
教育費がかかる家庭におすすめのふるさと納税返礼品(食品編)
| 返礼品 | ▶楽天ふるさと納税のページへ | 特徴 |
|---|---|---|
| 🍚 お米(縁のある複数地域) |   | 縁のある地域のお米を食べ比べ。家計に直結するありがたさ。 |
| 🌊 わかめ(大分県国東) |   | 大分県国東/海藻がどれもすばらしい。旅行で出会った絶品。 |
| 🍨 アイスクリーム(北海道) |   | 北海道のフレーバー豊富なセット。子供たち(大人も)のお楽しみ。 |
| 🧈 バター(北海道) |   | 洋菓子作りや朝食に。アイスとセットでだいたい選ぶことが多い。 |
教育費がかかる家庭におすすめのふるさと納税返礼品(生活雑貨編)
| 返礼品 | ▶楽天ふるさと納税のページへ | 特徴 |
|---|---|---|
| 🍽️ 波佐見焼(長崎県) |   | 器好きにはたまらない。見ているだけで楽しい。 |
| 🧼 白雪ふきん(奈良県) |   | 使い心地抜群。贈り物にも◎ |
| 🛁 今治タオル(愛媛県)・泉州タオル(大阪府) |     | 今後試してみたいアイテム。生活の質が上がる予感。タオルはいくらあっても困らない。 |
家計を助けながら、地域への応援にもつながるふるさと納税。 教育費がかかる時期こそ、こうした“暮らしに寄り添う返礼品”を選んでみてはいかがでしょうか。
まとめ
この記事では、ふるさと納税の基本的なしくみから、教育費がかかる家庭こそ活用すべき理由、そして我が家のリアルな使い方までご紹介しました。
制度を知っているだけで、家計の味方になるチャンスが広がります。 まずは控除上限額を調べて、気になる自治体や返礼品をのぞいてみるところから始めてみてください。
始め方の3ステップ
自治体のオリジナルサイトもありますが、もし複数の自治体に寄付をしたいのであれば、ポータルサイトを利用するほうが簡単にできます。
扶養家族の状況や収入によって控除上限額が違います。上限額を超えた寄付をすると、本当にただただ、寄付をしてその地域を応援しただけの状態で、税金の控除などはそのぶんはされませんので、必ず確認してください。
どの地域の、どんな返礼品を選ぶのかも、控除上限額も、ポータルサイトで全部できます。
ワンストップ納税制度を利用するか、もしくは確定申告をしないと、あなたがふるさと納税をした、ということは誰にも伝わらないので、税金の控除のしようがなくなります。
かならず、「私はふるさと納税をしましたので、税金の控除をお願いします」という意思表示が必要です。
「私はふるさと納税をしましたよ!税金を控除してくださいね!!」ということをお知らせするために、ワンストップ納税の制度を利用するか、確定申告をしてください。
教育費がかかる時期こそ、暮らしに寄り添う制度を味方につけて。 ふるさと納税が、あなたの家庭にとってちょっとした“助け”や“楽しみ”になりますように。
この記事が、ふるさと納税を始めるきっかけになったら嬉しいです。 家計の味方として、そして地域とのつながりとして、ふるさと納税を楽しんでみてください。
スポンサーリンク