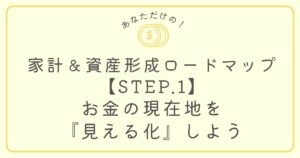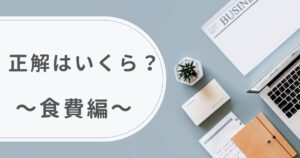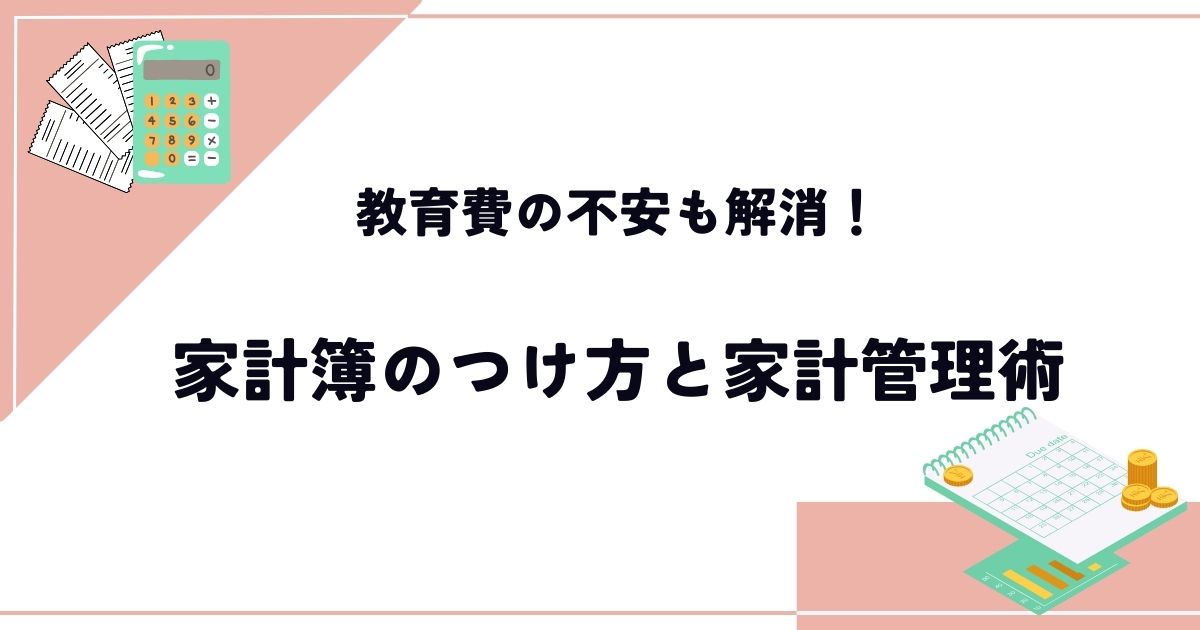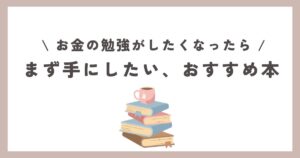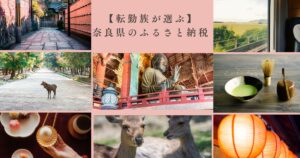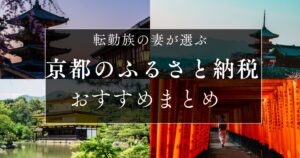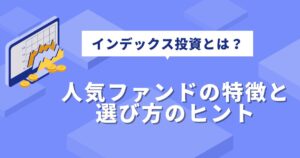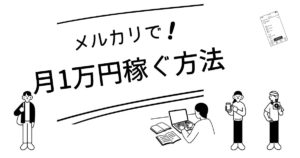「このままで、将来の教育費は大丈夫かな?」「中学受験って、やっぱりお金がかかるよね…」
そんな漠然としたお金の不安を抱えている方、いらっしゃいませんか? 今回は、そんな方に我が家流の家計簿のつけ方と家計管理術をご紹介します。
この記事でわかること
なぜ「家計の見える化」が必要なのか?
漠然としたお金の不安を具体的な数字に変えることは非常に大切です。
「中学受験をして、もし私立中学校に進学した場合、本当に家計は大丈夫?」という不安を解消するために、とにかくすべてを見える化してみましょう。
最初は明確だった不安の中身(例えば進学よりもまず中学受験準備段階の塾費用等をどの程度まで出せるのか、そして、進学後はどのくらいお金が必要なのか、家計は耐えうるのか)も、目標設定して実行していくうちに、なんのための行動なのかがわからなくなることがあるからです。
今後も安心して生活をするために、心配事や目標もすべて書いて、いつでも確認できるようにしておくことが大切です。
具体的な見える化の手順
①不安なことや目標を書きだそう
まずは、どんなことが心配なのか、不安に思うことなど些細なことでも構わないので、全部書いてみましょう。
そして、将来どうなりたいのか、どうしたいのか、という希望も全部書いてみましょう。
絶対にこれだけは譲りたくない、というラインなども考えてみて、それも書き出しておきましょう。
これは、希望を実現している最中に、だんだんと自分の目標を忘れてしまったり、どこまで頑張れば良いのかがわからなくなってしまうことが多いからです。
目標や夢は定期的に見直して、変更があればその都度その旨をあらためて書いておきましょう。
②家計の全体像を把握しよう
いよいよ目標の実現のための第1歩です。まずは今がどんな状態なのかを把握しましょう。
毎月の給料、ボーナス、東京都からの「018(ゼロイチハチ)サポート」などの助成金など、すべての収入源を手取り金額(振込金額)で明確に記入します。
固定費
住居費、光熱費(電気、ガス、水道)、通信費(インターネットプロバイダー料金、家族それぞれのスマホ代金)など、毎月(毎年)決まって出ていくお金です。
変動費
- 食費・外食費: お米、お酒、お菓子なども含め、食に関する全ての出費をここに入れます。
- 家事用品費: 日用品など。
- 被服及び履物費: 衣類や靴など。
- 保健医療費: 医療費控除やセルフメディケーション税制で使う可能性もあるので、細かく記録しています。
- 車関連費: ガソリン代や車のメンテナンス費用など。
- 教育費: 学費や定期代、部活動関連費用などもここに含まれます。
- 教養娯楽費: レジャー費だけでなく、自己研鑽のための書籍購入費などもここに入れています。
- その他: 上記に当てはまらない出費を記入します。
「なんとなく」のどんぶり勘定ではなく、まずは1〜2ヶ月だけでも、実際に記録してみることが大切です。手書き、家計簿アプリ、スプレッドシートなど、ご自身に合ったツールはどんなものでも構いません。
▼私が長年愛用している家計簿はこちら!年収の10倍以上にお金を増やすアイテムの一つといっても過言ではありません!!【現在2026年度版は予約受付中です】
③定期的な「見直し」と「改善」で無理なく続けよう
自分で決めた期間(おすすめは月に一度、メインで使用しているクレジットカードの締め日や、給料日などを区切りにするとわかりやすく、把握しやすいです。)で一度家計簿を締めて、その都度振り返り(見直し)、もう一度戦略を練り直しましょう(改善)。
- 1か月単位だけではなく、年間のまとめページも作る。
家計簿は、1か月単位だけではなく、1年のまとめページも作っておきましょう。
1か月ごとのまとめを12か月分、ただ合計していくだけのページで問題ありません。
例えば会社員で、基本的には申告の必要がないという場合でも、医療費控除やふるさと納税の申告、住宅ローン減税など、自分で確定申告をするシーンがあるかもしれないので、それを考えると、「1年のまとめページ」は、その年の1月1日から12月31日までを1年とカウントするのが良いです。 - 年間の収入や支出予定をたてておく。
学校や習い事(予備校や塾も含む)の月謝などはあらかじめ年間引き落とし予定がわかることが多いです。そのようなものは、すべて年間のまとめページなどに記載して、心の準備や実際のお金の準備もしておきましょう。
もしわからない場合も、一応、このくらいかかるという見積をどこかに書いて(高めの見積がおススメ)準備しておきましょう。
帰省やバカンスなどの娯楽費等も、予算(こちらも高めの設定がおすすめ)で良いので書いておきましょう。
ボーナスや助成金といった、入ってくるお金(収入)も、わかる範囲でざっと記入しておきましょう。 - 年間の目標をたてておく。
このくらいの収入があるだろうという予定と、現状の貯蓄などを考えて、支出は収入以内にしたいのか、子供の受験や入学があるから、今年は支出のほうが多いだろうから貯蓄をいくら切り崩す、といったような目標をたてておきましょう。
面倒になることも多いとは思いますが、自分が一番楽しく、楽にできるスタイルを見つけて、家計簿をつけましょう。
記録した家計簿を見ながら、その月の収入と支出がいくらだったかを把握します。
(もし、使途不明金がある場合は、後から判明した時のことを考えて、自分でわかるようにチェックしておきましょう。)
この振り返りを行うことで、漠然としたお金の不安を解消し、翌月以降の使い方の調整に繋げています。
家計簿1か月分を締めたら、その都度「年間のまとめページ」にも記載しましょう。
月間でも「見直し」はしましたが、年間でも同じように「見直し」をして、年ベースで考えたときに、12月末までの残りの月で、目標達成できそうかなどチェックしておきましょう。
月ごとに、「今月はどの費目の何にいくら使った」ということを正確に把握しましょう。
そして、そのペースでいけば年間の予定から大幅にずれが生じそう、ということであれば、翌月からはそれをどうしていけば良いのか、考えてみましょう。そして翌月以降実践してみましょう。
もちろん、目標も、その都度変えても問題ありません。
例えば、特に子供の受験期などは教育費が突出するのは当然です。
月単位での細かな見直し⇔改善ももちろん大切ですが、もっと長い目で見て、この年は赤字でも問題ない、というような判断をしても、トータルで見たときに目標が達成できれば、良いです。
また、「お金を増やす」という場面では、「節約」以外にも、「投資」など、他の手段があるということも再確認してみましょう。
我が家の家計管理方法
我が家が選んだ「無理なく続く」家計簿ツール
- PCでの入力や家計簿アプリを使う方も多い中、我が家が長年愛用しているのは、
市販の「手書きタイプ」の家計簿です。 - 毎年「サンキュ! みるみる貯まる!家計ノート(ベネッセ刊)」をリピート購入しており、
価格も340円と非常に手頃です。 - なぜ手書きにこだわるかというと、パソコンをいちいち立ち上げて入力するのが面倒なこと、
そしてアナログに手で書いていく方が性に合っているからです。 - 以前は、一般的な手書き家計簿のやり方として紹介されているような、大学ノートに自分で線を引いて
フォーマットを作る方法も試しました。しかし、毎月同じフォーマットを手書きするのが面倒な上、
線を真っ直ぐ引けているかといった細かな点が気になってしまう私の性格には合いませんでした。
市販の家計簿はあらかじめ枠が決まっているので、そこに記入するだけでよく、微調整もしやすいため、
ストレスなく続けられています。 - 決済方法の管理: ほぼ99%をクレジットカードで決済しているため、現金で支払った時だけ分かるように
マークをつけています。何で決済したのかを把握しておかないと、後で確認するのが難しくなるためです。
▼私が長年愛用している家計簿はこちらです!年収の10倍以上にお金を増やすアイテムの一つといっても過言ではありません!!【現在2026年度版は予約受付中です】
我が家流「お金の使い道の把握」と「調整」
- 厳密な月ごとの予算は設定していませんが、長年の記録(20年以上続けている家計簿)から家計の「傾向」を把握することを重視しています。
- 例えば、「先月は食費がいつもより多かったから、今月はもう少し意識して調整しよう」といったように、過去の実績に基づいた緩やかな調整を行っています。
- 基本的には、どの費目も無理に節約しようとは考えていません。なぜなら、どれも私たち家族にとって必要だと考えているからです。
- 大切なのは、その出費が「浪費」なのか「消費」なのか「投資」なのかを考えることです。例えば、友人とのカフェ代も、そこから刺激的な話を聞いて新しい挑戦に繋がったり、美味しいケーキで気分転換し仕事に活かせたりするなら、それは「投資」と捉えることもできます。他人の「これは削るべき!」といった節約論に振り回される必要はない、というスタンスでいます。
「大きなお金の動き」の共有と管理
- 特に中学受験や私立学費といった教育費、住宅、老後資金など、将来の大きな出費については、夫婦間で明確に共有しています。
- 具体的には、Googleスプレッドシートで家計共有ファイルを作成しています。子どもたちの学費の引き落とし日や金額はもちろん、クレジットカードや光熱費などの口座引き落とし情報、その他夫婦で共有しておきたい大きめの入出金が判明した時点で、すぐに共有ファイルに記録するようにしています。
- これにより、「いつ、いくら、何で引き落としがあるか」を常に把握でき、漠然としたお金の不安を解消し、必要な資金を確実に準備できています。
家計の見える化は「安心」への第一歩
家計簿は単なる記録ではありません。
それは未来を計画し、漠然としたお金の不安を具体的な行動に変え、最終的に揺るぎない自信へと繋げるための
強力なツールです。
私も長年家計簿をつけ、中学受験という大きなライフイベントを経験する中で、その大切さを痛感してきました。
「完璧にこなさなければ」とプレッシャーを感じる必要はありません。
まずは「お金がどこへ行ったか」を把握する、できることから一歩ずつで大丈夫です。
あなたもきっと、家計の見える化を通じて、安心して前に進めるはずです。