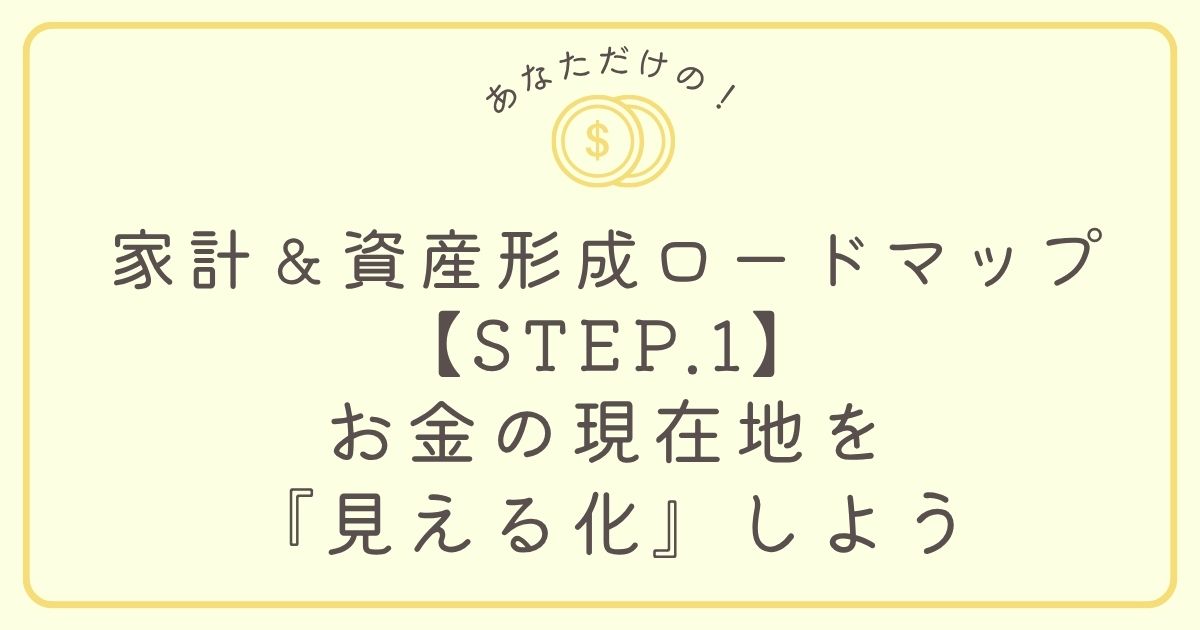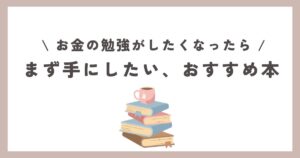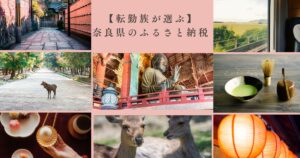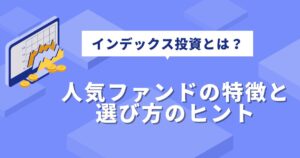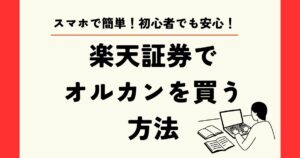さて、今回からいよいよ「あなただけの家計&資産形成ロードマップ」を具体的に描き始めるステップに入ります。最初のテーマは、現状把握。つまり、あなたのお金の「現在地」を知る方法です。
この記事を読むと、あなたのお金の「現在地」が明確になり、未来への第一歩を踏み出すことができます。具体的には、以下のことがわかります。
なぜ今、「あなたのお金の現在地」を把握する必要があるのか?
「見える化」が、お金の不安を消す第一歩
現段階で、「あと〇か月で〇〇円必要なのに、どうしよう!」といった差し迫った危機はもちろん不安ですが、お金に関する不安のほとんどは、「よく分からない」「把握できていない」という漠然とした状態からくるものではないでしょうか?
例えば、こんな風に感じたことはありませんか?
- 「このペースでお金を貯めて、子どもたちの希望する学校に通わせられるのかな…」
- 「大学費用って、一体いくらくらい用意すればいいんだろう?」
- 「もし病気やケガで収入が減ったら、生活は大丈夫なのかな?」
- 「老後って何歳から、どのくらいの貯蓄があれば安心して暮らせるんだろう?」
これらの漠然とした不安を解消するためには、具体的な「見える化」の作業が必要になります。
(例)
- 「この学校に通わせるなら、6年間でこのくらい必要。今の貯蓄ペースだと足りないから、運用するか、仕事を増やすか、あるいはもう少し学費を抑えられる学校を選ぶか…」
- 「まずは公的な保障や保険でどこまでカバーできるかを調べ、足りない部分を把握する。」
- 「老齢年金の概算を把握した上で、老後の生活に必要なお金を確認し、それまでにどう資産を築くか計画を立てる。」
このように、一つ一つの不安を棚卸しし、それをライフプランニングシートなどを用いて「見える化」すること。そうすることで、漠然とした不安が具体的な課題として明確になり、次の一歩を踏み出すための具体的な対策が立てられるようになります。
この「見える化」の作業は、地味に感じるかもしれませんし、普段から家計簿などをつけていない場合は時間もかかるかもしれません。しかし、未来の計画を立てる上で決して避けては通れない、非常に重要な作業です。
一度取り組んでみると、意外な発見があったり、ゲームのように面白く感じたりする場合もあります。もし「自分でやるのはどうしても面倒…」ということであれば、私のようなFPがお手伝いすることも可能ですし、他人にはどうしても情報を知られたくない、という方であれば「ウェルスナビのようなロボアドバイザー」などのツールを使うことも、効率的な方法の一つです。
資産形成は「現在地」を知ることから始めよう!
お金の不安を解消し、未来の計画を立てるために「見える化」が不可欠だとお話ししました。この「見える化」において、そしてこれから資産形成を本格的に進めていく上で、最も重要なカギとなるのが、あなたの「現在地」を知ることです。
これはまるでカーナビと同じです。どんなに素晴らしい目的地(目標)を入力しても、現在地がわからなければ、目的地までの正確な道のりは分かりませんし、たどり着くこともできません。
上記で家計簿の話も少し触れましたが、必ずしも厳密な家計簿である必要はありません。それでも、毎月(あるいは年間を通して)いくらの収入があり、いくらの支出があるのか、そしてその支出の内訳がどうなっているのかを把握することが、あなたの「現在地」を知る上で不可欠になります。
私たち夫婦は、資産運用を仕事にし、自己研鑽も積んでいたので、知識や経験があったことは間違いありません。しかし、そんな私たちでさえ、まず夫婦で現状を詳細に共有することから始めました。そして現在でも、お互いの状況を常に把握できるように努めています。
家計の収支を『見える化』する具体的方法と注意点
とにかく記録しよう!把握しよう!:継続は力なり!そして「怒らないこと」
「見える化」をする上で、そしてこれから資産形成を進めていく上で、カギとなるのは「現在地を知る」こと。そのために大切なのが、とにかく「記録する」「把握する」ことを継続することです。
私は一貫して「紙の家計簿」に家計の収支を記録していますが、それは私個人のこだわりです。夫とも家計の状態は常に共有していますので、私が紙の家計簿で日々記録して1か月分をまとめたものを、共有のエクセルファイルに入力し、夫はそちらで全体像を把握できるようにしています。
この方法を継続できているのは、夫が決して家計の状況について「怒ったりしない」からだと感じています。 「これはこんなにかかるの?使いすぎじゃないの?」といった、ドラマや漫画でよくあるようなことを、これまで一度も言われたことがありません。だからこそ、安心して家計簿を共有し、継続できているのだと思います。
家計簿である必要はありませんが、家計の収支を把握するためのツールとして、まずは家計簿を例に考えてみましょう。
何よりもまず最重要なポイントは、「とにかく続けること」です。
家計簿をつけることは、あくまでも手段であり、目的ではありません。このことを常に意識してください。もし、途中で「家計簿、めんどくさい!」と感じてしまったら、思い出してください。完璧を目指す必要は全くないのです。なぜ今、家計簿をつけるのか?それは、未来のあなたのために「現在地」を知るため。そう自分に言い聞かせながら、おおまかでもいいので、まずは記録を継続してみましょう。
記録を続けていくと、思っていた以上に使っていたり、逆に使っていなかったりするものが見えてきます。まるで、家計が数字で語りかけてくるようで、案外楽しく感じられるかもしれません。
もし、将来的に「もう少し貯蓄を増やしたい」「〇〇の費用を削りたい」と思った場合も、何にどのくらい使っているか、どの費目を削るべきかというのは、家計簿をつけて「見える化」できて初めて具体的にわかるものです。
まずは「自分で何にどのくらい使っているか予想してみて、それが合っているか」という、自分だけのゲーム感覚で家計簿をつけてみるのも良いかもしれませんね。
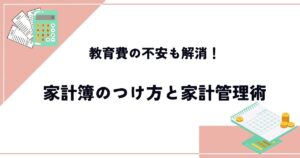
あなたに合った「記録ツール」を選ぼう
家計の収支を「見える化」するための記録ツールには、様々な種類があります。最も大切なのは、あなたが「一番使いやすい」と感じ、そして「飽きずに続けられる」ものを選ぶことです。
ここでは、代表的な家計簿ツールの種類と、それぞれのメリット・デメリットをいくつかご紹介します。
| ツールの種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 手書きのノート・市販の家計簿 | ・書くことでお金の流れを実感しやすい ・レイアウトやカテゴリ設定の自由度が高い | ・集計作業や日々の記録に手間がかかる |
| Excel・スプレッドシート | ・計算の自動化が可能 ・あなたの変化に合わせて、形を自在に調整できるカスタマイズ性の高さ | ・初期設定に手間がかかる場合がある ・自分で管理・更新する必要がある |
| 家計簿アプリ (マネーフォワードME、Zaimなど) | ・銀行口座やクレジットカードとの連携がスムーズ ・自動で収支を分類してくれる | ・連携のミスやタイムラグがある可能性 ・初期設定や学習に手間がかかる場合がある |
私は、自由度が高く、その中では比較的気軽に続けられる「市販の家計簿」をメインに、紙で日々の収支を記録しています。夫と共有する際はスプレッドシートを活用し、また、総合的なライフプランニングに必要なすべての情報管理はExcelで細かく行っています。
しかし、私の周囲を見渡すと、家計簿アプリを使っている方が圧倒的に多い印象です。やはり「書く」ことに手間がかかる分、アプリで「シュッと素早く管理できる手軽さ」は、忙しい現代において非常に魅力的ですよね。
どのツールが「正解」ということはありません。あなたの性格やライフスタイルに合わせて、まずは気になるツールで「とにかく家計簿を継続してつけること」を最優先に考えましょう。
その小さな一歩が、きっとあなたの新しい家計管理への道を確実に切り開いてくれるはずです。
すべての資産を一覧で把握しよう
家計簿をつけることで、日々の暮らしにおけるお金の流れがだんだんと見えてきたでしょうか。 「見える化」は、まだこれで終わりではありません。
次に見ていくのは、お財布から出ていくお金(家計の収支)だけでは見えにくい、「預貯金」や「投資商品」といった、あなた自身の持っている資産全体です。
預貯金(普通預金、定期預金など)、株式、投資信託、年金(iDeCo、企業型DCなど)、不動産、保険の積立部分など、あなたが現在持っている全ての資産をまずは洗い出してみましょう。
そして、同時に借りているお金、つまり「負債」も明確にします。住宅ローンや車のローン、奨学金など、返済が必要なお金も全てリストアップしてください。
資産の棚卸しをすると、一時的にお金が増えたり減ったりすることに一喜一憂しがちですが、大切なのは「点」ではなく「線」で捉えること。広い視野で、俯瞰して全体像を把握するようにしましょう。
資産棚卸しにおすすめのツール
家計簿の記録に慣れてきたら、次に取り組むのは**資産全体の「棚卸し」**です。預貯金だけでなく、投資信託や株式、年金資産、さらにはローンなどの負債まで、すべてを一覧で把握することで、あなたのお金の全体像がより鮮明になります。
この資産の「見える化」を強力にサポートしてくれるのが、多様な資産管理アプリです。家計簿管理アプリと連携できるものも多く、複数の金融機関の情報を自動で集約してくれるため、手間なく管理できるのが大きなメリットです。無料で使えるアプリも多いので、ご自身のライフスタイルや目的に合ったものを見つけて、賢く活用していきましょう。
以下に、代表的な資産管理アプリの特徴を比較表にまとめました。
| アプリ名 | 主な特徴・強み | メリット | デメリット/注意点 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|---|
| マネーフォワードME | 連携サービス数No.1の家計・資産管理アプリ。支出自動分類やグラフ化が充実。 | ・2,000以上の金融機関・サービスと自動連携可能 ・資産全体の推移や内訳をグラフで視覚的に把握できる ・レシート撮影機能で支出管理も手軽 | ・無料版は連携口座数に制限あり(10件まで) ・無料版は過去1年分のデータまでしか閲覧できない ・有料プラン(月額500円~)で全ての機能が利用可能 | ・複数の金融機関口座や投資商品をまとめて管理したい方 ・家計も資産も両方まとめて管理したい方 ・手入力の手間を減らしたい方 |
| Moneytree(マネーツリー) | 無料で広告なし。シンプルで信頼性の高いデータ自動連携が魅力 | ・無料で金融機関を無制限に連携可能 ・広告表示がなくストレスフリーで利用できる ・登録データは永年保存される ・「個人」「経費」に分けて資産管理ができる | ・資産の損益表示機能は搭載されていない ・レシート読み取り機能は有料プランから ・連携サービス数が最大手と比べるとやや少ない | ・シンプルで無料での利用を重視する方 ・電子マネーや共通ポイントもまとめて管理したい方 ・広告表示を避けたい方 |
| Zaim(ザイム) | 家計簿機能が非常に充実。手入力やレシート撮影も簡単で直感的。 | ・レシート撮影で簡単にデータ入力が完了する ・無料版でも自動連携できる金融サービスの数は無制限 ・デザイン性が良く、初めてでも使いやすい ・家計管理に役立つ多機能性 | ・無料版ではカテゴリ編集に制限あり(有料: 月額480円~) ・無料版は資産推移のデータ閲覧が1ヶ月分のみ ・無料版はデータを手動更新できない | ・初心者で家計簿から始めたい方 ・現金払いが多い方や連携していない支払い方法も管理したい方 ・使う金融機関やECサイトが多い方 |
| OsidOri(オシドリ) | 夫婦・家族間の共有に特化した資産管理・家計簿アプリ。 | ・明細ごとに相手に見せるかどうかを決められる ・共有したいお金とプライベートなお金を分けられる ・目標貯金額に対し、夫婦それぞれの貢献度を設定できる ・家族貯金機能で共有の目標設定が可能 | ・レシート読み込み機能はない ・無料版は連携口座数に制限あり(1アカウント7件まで) ・無料版は過去データ閲覧が最大6ヶ月まで | ・夫婦や家族で一緒に家計や資産の管理をしたい方 ・共有する情報とプライベートな情報を分けたい方 |
| OneStock(ワンストック) | 野村證券とマネーフォワードが共同開発。主に投資資産の一元管理に強み。 | ・無料で無制限に金融機関と連携可能(野村證券口座不要) ・ポートフォリオや資産の寿命管理、市場分析機能あり ・不動産などの金融以外の資産も一元管理できる ・配当カレンダー機能がある | ・無料版では資産データの詳細確認に制限がある(更新頻度が低いなど) ・クレジットカードや電子マネーとの連携は未対応 ・有料版(月額550円)で幅広い機能が利用可能になる | ・株式投資を中心に金融資産を管理したい方 ・投資資産のポートフォリオ管理を重視する方 ・複数の証券口座や金融機関の資産をまとめて見たい方 |
あなたに最適な「見える化」の方法を見つけよう
様々な資産管理アプリをご紹介しましたが、正直なところ「これが唯一の正解!」というツールはありません。なぜなら、最も大切なのは、どのツールを選ぶかではなく、家計簿と同じく「継続して資産の現在地を把握すること」だからです。
私自身も、日々資産の管理を行っていますが、実は資産管理アプリはあまり使っていません。主に、Excelのスプレッドシートを活用して、全ての資産と負債を一覧で管理しています。
私がこの方法を選んでいる理由は、以下の2点です。
- 徹底的なカスタマイズ性: 預貯金や株式、投資信託、確定拠出年金(iDeCo/企業型DC)、さらには不動産や住宅ローン残高、積立型保険の評価額など、保有している多岐にわたる資産と負債を、自分にとって最も分かりやすい形で自由にレイアウトし、集計できるからです。
- 「手書き家計簿」と同じ実感: 毎月末に各金融機関の残高や評価額を確認し、手入力でシートに記録する作業は、まさに手書きの家計簿と同じように、「自分の資産を着実に把握している」という確かな実感につながります。数字が少しずつ増えていくのを目で追うことは、継続のモチベーションにもなっています。
この地道な作業によって、私は月ごとの純資産額(資産から負債を引いた実質的な資産)の推移を「点」ではなく「線」で捉えることができています。一時的な市場の変動に一喜一憂することなく、長期的な視点で資産形成の進捗を確認できるのは、精神的な安定にも繋がっています。
どんなツールでも構いません。まずは、あなたにとって「これなら続けられそう」と感じる方法やツールを一つ選んで、資産の棚卸しを始めてみてください。完璧を目指す必要はありません。大切なのは、あなたの「お金の現在地」を把握し続けることです。
【Step 1】で見える化した『現在地』をどう活かすか
ここまでのステップで、あなたはご自身の家計の収支と資産状況という「現在地」を、しっかりと『見える化』できたのではないでしょうか。
この「見える化」によって手に入れた具体的な数字は、まさに「あなただけのロードマップ」を描くための最も重要な情報となります。目的地(あなたの希望する未来)へ、今どの位置から、どれくらいのペースで、どんな道筋で進んでいけば良いのか、その全体像が見えてくるはずです。
目先の数字に一喜一憂せずに、例え一時的に保有資産の総額ががくっと少なくなることがあっても慌てず、逆に、大幅に増えることがあったとしても、舞い上がってしまったり、計画から逸脱するような行動に出たりせずに、
目標がどこなのか、今自分がどの位置にいるのかを常に意識しながら行動しましょう。
【Step 2】へ!あなたのロードマップを描き始めよう!
今回のSTEP1では、「見える化」することがあなたの希望への道を踏み出す第1歩であり、なかなか面倒な『「見える化」の具体化』についても、便利なツールを利用する手もあるというお話をいたしました。
いずれにしても、未来にむかって勇気を出して一歩を踏み出されたみなさんはすばらしいです。
もしうまくいかなくて別の方法や別のツールを使うことになったとしても、何一つ無駄にはなっていません。
どんなツールがあるのかを知ること、ツールを使うことで自分の資産を洗い出したであろうそのことがもうすでに先に進んでいるからです。
さあ、次回は目標をどのように具体化していくのか、目標金額を明確にする方法など、目標設定についてのお話をいたします。
お楽しみに!