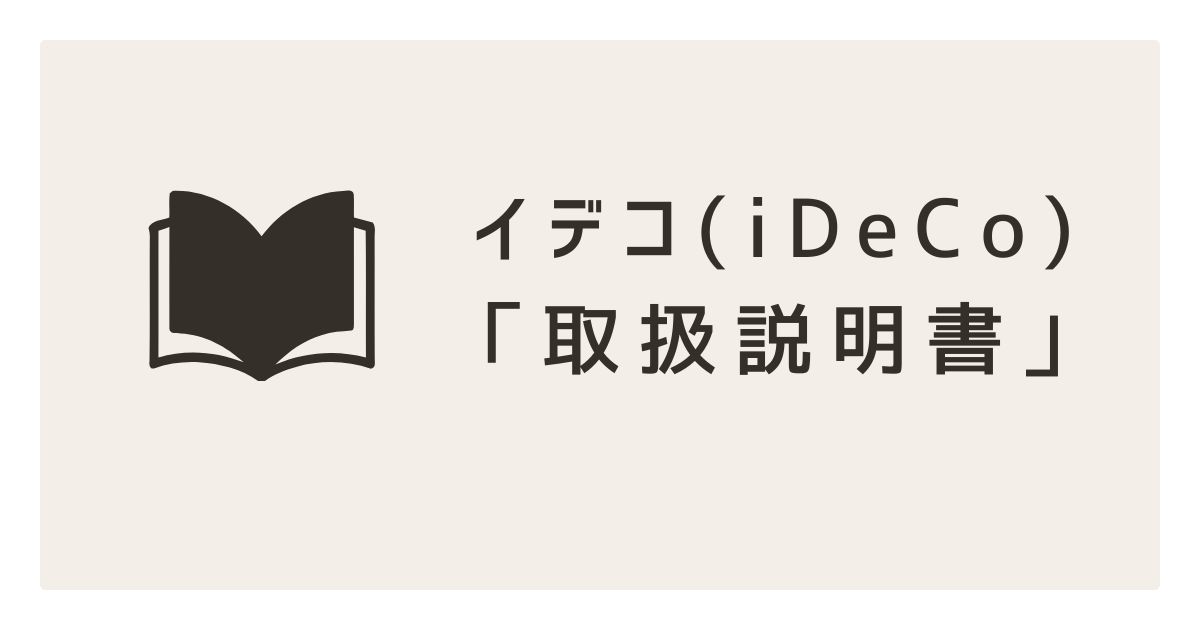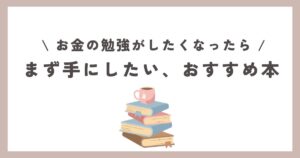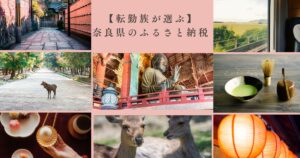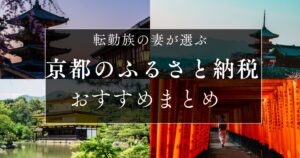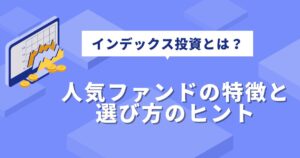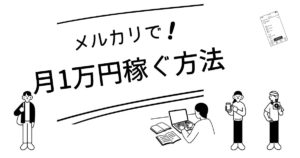「NISA(ニーサ)」「iDeCo(イデコ)」
という言葉を昨今よく聞きます。
「年金だけでは老後の生活はかつかつらしい」「2000万いるらしい」
ということも、ずっと昔からよく聞きます。
おそらく多くの人が、こう思っているはずです。
「将来のお金、どうしよう?」
「老後が不安…」
「年金だけじゃ足りないって聞くけど、どうすればいいの?」
そんな悩みを解決できるかもしれないのが、「iDeCo(イデコ)」です!
今回は、イデコ(iDeCo)の取扱説明書、私オリジナルバージョンを作りました。
興味はあるけど恥ずかしくて誰にも聞けないけど、調べるのもめんどくさいし、簡単なことでいいから知りたいな。という方におすすめです!
お楽しみください。
そして、この「取扱説明書」が、iDeCoという強力なツールをあなたが理解し、賢く資産形成を進めるための第一歩となれば大変嬉しいです。iDeCoがあなたの資産を守り、増やすツールの選択肢の一つに仲間入りすることになれば幸いです。
この記事でわかること
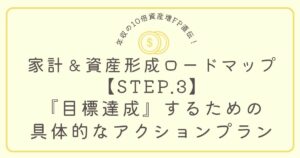
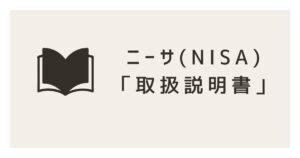
「イデコ(iDeCo)」の性格(特徴)
イデコ(iDeCo)ってどんなもの?
「年金だけでは老後の生活が不安」とよく聞きますよね。
将来もらえる公的年金は、ゆとりある生活を送るためには少し足りないかもしれません。
そこで、自分で作る「じぶん年金」として、iDeCoがあります。
iDeCoは、自分で決めたお金を積み立てて、自分で運用し、老後のためのお金を準備する制度です。
簡単に言うと、「国がつくった、おトクな資産形成ツール」のようなものです。
この制度には、3つの大きなメリットがあります。
iDeCoの超シンプルな3つのメリット
iDeCoには、3つの大きなメリットがあります。
例えば月に1万円をiDeCoで運用したとしたら、年間12万円、所得から引いてもらえます。
その分かかるはずだった税金がかからなくなります。
(会社員の方は年末調整、自営業の方は確定申告で手続きができます。)
iDeCoは基本的には60歳になるまで解約・売却できませんが、分配金などが発生した場合も、それにかかる税金はかからず、まるまるその分再投資されます。(通常、投資の利益には約20%の税金がかかります。)
受け取り方によって、退職金と同じような扱いになったり、年金として扱われたりすることで、税金が安くなります。
シミュレーション:どれくらいお得になるの?
では、具体的に数字を出して、どのくらいお得になるのかを見てみましょう。
【例えば年収650万円の人の場合】
- 年収650万円から給与所得控除などを引いた、課税される所得(課税所得)は約400万円になります。
- (※この400万円に所得税や住民税がかかります)
- 年間24万円(2万円 × 12ヶ月)をiDeCoで運用します。
- 課税所得からさらに24万円が控除されます。
- iDeCoの節税効果により、所得税と住民税を合わせて、年間で約7.2万円も税金が安くなります!
- (※所得税率20%+住民税率10%で計算した場合)
国民年金基金連合会 iDeCo公式サイトにて、年収、毎月の積立額、積み立て開始年齢を入力するだけで、税額がいくらくらい軽減されるのか、積み立て総額がいくらになるのかなどのシミュレーションができます。ぜひいろんなケースのシミュレーションをしてみてください。
知っておきたいiDeCoの注意点(デメリット)
うれしいポイントがたくさんあるiDeCoですが、もちろん注意する点もあります。
- 原則60歳まで引き出せないこと
iDeCoは、将来受け取る年金を少しでも多くなるように自分で運用しよう、というものなので、原則60歳まではひきだすことができません。 - 元本割れのリスクがあること
運用をどの金融商品を使うかでもかなり変わりますが、預貯金ではなく、何かしらの商品で運用をするので、場合によっては元本よりも少ない金額になっている可能性もゼロではありません。 - 手数料がかかること
iDeCoには、大きく分けて3種類の手数料がかかります。
①加入・移換時にかかる手数料(初回のみ)
②運用中に毎月かかる手数料
③資産を受け取るときにかかる手数料
- 加入・移換時にかかる手数料
- 加入時・移換時手数料(2,829円、税込):
- iDeCoに新規で加入する際や、企業型DCからiDeCoに資産を移し換える際に、国民年金基金連合会に支払う手数料です。
- この手数料は、どの金融機関を選んでも金額は一律で、初回の掛金や移換された資産から差し引かれます。
2.運用中に毎月かかる手数料
この手数料は、さらに以下の3つに分けられます。
- 国民年金基金連合会への手数料(105円、税込):
- 掛金の収納や加入者情報の管理にかかる手数料です。
- これもどの金融機関を選んでも金額は一律で、毎月必ずかかります。
- 信託銀行への手数料(66円、税込):
- iDeCoの資産を管理する信託銀行に支払う手数料です。
- これもどの金融機関を選んでも金額は一律で、毎月必ずかかります。
- 運営管理機関への手数料(0円~):
- これが金融機関によって金額が異なる手数料です。
- 金融機関が、運用商品の選定や情報提供などのサービスを行うためにかかる費用です。
- 最近は、SBI証券、楽天証券、マネックス証券などの大手ネット証券は、この手数料を無料にしているところが多いです。
つまり、iDeCoで毎月かかる手数料は、どの金融機関を選んでも最低171円(105円+66円)は必ずかかりますが、運営管理機関手数料が無料の金融機関を選ぶことで、それ以上の費用はかかりません。
3. 資産を受け取るときにかかる手数料
- 給付手数料(440円、税込):
- 60歳以降にiDeCoの資産を受け取る際、給付1回ごとにかかります。
- 例えば、一括で受け取るなら1回分、分割で受け取るならその都度かかります。
これらの手数料は、iDeCoの税制メリット(所得控除、運用益非課税)と比べて、多くの場合、十分に元が取れる金額だと言えます。特に運営管理機関手数料が無料の金融機関を選べば、コストを抑えて運用できます。
iDeCoにはメリットもデメリットもありますが、資産形成の全体像を知っておくと制度の選び方がラクになります。
両学長の『お金の大学』や、山崎元さんの『難しいことはわかりませんが…』は、初心者にもわかりやすくておすすめです。
▼図解でわかりやすくておすすめ!
▼会話形式で読みたい方はこちらもおすすめ!
iDeCoの始め方:たった3ステップ
始める前に!
①加入資格と掛け金の上限を確かめましょう!
国民年金の被保険者種別(自営業者なのか、会社員なのか、専業主婦なのか・・など)や、お勤め先の企業年金の違いによって、掛け金の限度額が異なります。
②自分の性格(運用に対してどのくらいリスクをとれそうか)、将来について考えてみましょう。
自分の将来について、よく考えて、将来どうなりたいのかを考えましょう。そうなるためにはいくらくらいの資金が必要なのか、そして、自分が資産運用するにあたって、どのくらいのリスクをとれそうかなども改めて考えておきましょう。ライフプランニングをしてみるのがおススメです!
金融機関を選びましょう。
iDeCoを取り扱う金融機関(運営管理機関といいます)はたくさんありますが、加入できるのは1社だけです。
金融機関ごとに取り扱っている運用商品やサービス内容が異なりますので、よく比較検討しましょう。
事前に、自分のかけることのできる上限金額を把握した上で、いくら毎月積み立てるのかを決めましょう。
(年に1回金額の変更ができます。)
事前に、自分が60歳までにどのくらいの資金をiDeCoで補えばいいかをよく検討した上で、そしてどのくらいのリスクをとれるのか等もよく考慮した上で、どんな商品で運用していくのかを決めましょう。
(運用商品の変更はいつでもできます。回数の制限もありませんが、解約に費用が掛かる商品などもあるので、チェックしておきましょう。)
簡単に思えますが、60歳まで解約できないことなどもとても気になるし、パッと飛びつけるものでもないと思います。
もし不安なことがあれば、周りの信用できる金融機関やFPなどに相談しつつ、検討してみてください。
iDeCoはあなたにとっての”じぶん年金”
さて、私の「イデコ(iDeCo)の取扱説明書」はこれで終了です。
いかがでしたでしょうか。
iDeCoは始めるかどうか、自分で選べる制度です。まずは、ご自身の未来のために、少しでも考えてみませんか?