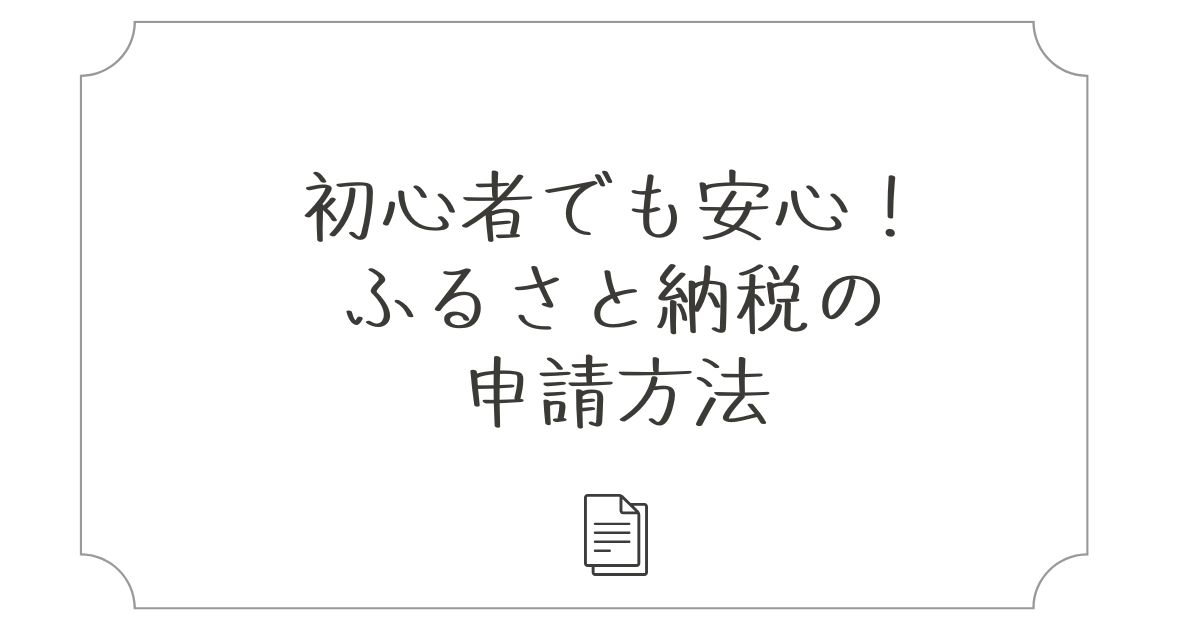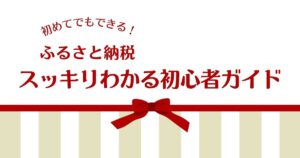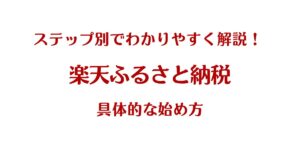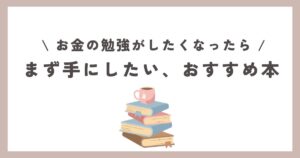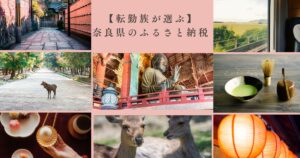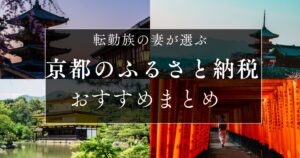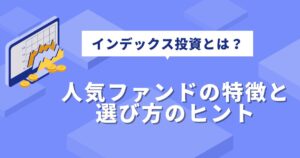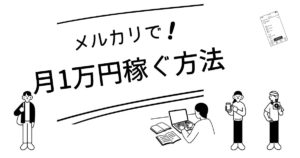ふるさと納税、はやめにおわらせたから気が楽~



ふるさと納税、「寄付しました」で終わらせるのは危険です!
実は、税金の控除を受けるためには「申告」または「申請」が必要です。
この記事では、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」について、それぞれの違い・メリット・手続きの流れを初心者にもわかりやすく解説します。
この記事を読むとわかること
2種類ある!ふるさと納税の申請方法
実は、ふるさと納税をしただけでは税金の控除は受けられません。
「私は寄付しましたよ!」ということを、きちんとお知らせ(申告)する必要があります。
申告しないと、自治体や税務署側ではあなたが寄付(ふるさと納税)をいくらしたのか等把握できないため、控除の手続きがされないのです。
この“申告”の方法として代表的なのが「確定申告」。 寄付した金額を申告することで、所得税や住民税から控除される仕組みです。
そして、条件がそろえば自分で確定申告をしなくても良いのが「ワンストップ特例制度」です。
所得税は税務署(国)が、住民税は自治体(市区町村)が担当しています。 そのため、申告をしないと、どちらの機関もあなたの寄付を把握できず、控除がされないのです。
ふるさと納税の申請方法には、主に「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の2種類があります。どちらを選ぶかは、あなたの働き方や寄付の件数によっても変わります。
「自分はどちらの申請方法を選べばいいの?」と迷っている方のために、ワンストップ特例制度と確定申告の違いを表にまとめました。それぞれの特徴を比較して、あなたに合った方法を選んでみてください。
📝 ワンストップ特例制度と確定申告の違いを比較
| 比較項目 | ワンストップ特例制度 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 控除される税金 | 住民税のみ控除 | 所得税還付+住民税控除 |
| 対象者 | 会社員などで確定申告不要な人 | 自営業、副業あり、医療費控除など申告が必要な人 |
| 寄付先の数 | 5自治体以内 | 制限なし |
| 手続き方法 | 申請書を自治体に提出(1月10日必着) | 税務署に確定申告(2月〜3月) |
| 必要書類 | 申請書+マイナンバー確認書類 | 寄附金受領証明書+源泉徴収票など |
| メリット | ✅手続きが簡単・申告不要 | ✅控除額が大きくなる場合もある/柔軟に対応できる |
| 注意点 | ⚠️6自治体以上だと使えない/期限厳守 | ⚠️書類の準備が必要/申告時期が限られる |
あなたはどちらを選ぶべき?
✅ 会社員で、ふるさと納税以外に申告する必要がない方は「ワンストップ特例制度」がおすすめです。
✅ 自営業や副業がある方、6自治体以上に寄付した方は「確定申告」で申請しましょう。
いかがでしょうか?
会社員で、ふるさと納税以外に申告する必要がない方は「ワンストップ特例制度」が便利です。一方で、6自治体以上に寄付した方や、副業・医療費控除などで確定申告が必要な方、1/10までの期限に間に合わなかった方などは「確定申告」で申請しましょう。
それぞれの制度にメリット・注意点がありますので、あなたの状況に合わせて選んでみてくださいね。



ふるさと納税の基本がまだあやふやかも?心配!



手続きの前に、制度の仕組みをサクッとおさらいしておきましょう。
👉ふるさと納税の仕組みを初心者向けに解説したガイド(控除の仕組みや寄付上限をわかりやすく解説)
📝ワンストップ特例の申請方法
ワンストップ特例制度を利用するには、申請書の提出とマイナンバー確認書類の準備が必要です。 ここでは、申請の流れや提出期限について解説します。
以下のステップに沿って進めれば、申請はスムーズに完了します。
寄付後にポータルサイトからダウンロードするか、自治体から郵送される申請書を使用します。
申請書は寄付ごと(自治体ごと)に提出が必要です。
氏名・住所・マイナンバーなどを記入します。印鑑は不要です。
マイナンバーカードのコピー、または通知カード+本人確認書類(運転免許証など)を準備します。
郵送またはオンライン申請(対応している自治体のみ)で提出します。
※提出後、届いた控えは保管しておきましょう
⚠️ ワンストップ特例制度の提出時の注意点
ワンストップ特例制度の申請は簡単ですが、提出時にいくつか注意点があります。 以下のポイントを押さえて、申請ミスを防ぎましょう。
- 提出期限は「翌年1月10日必着」
→ 郵送の場合は、到着日が基準です。ポスト投函ではなく、自治体に届く日が1月10日以内である必要があります。
- 寄付した自治体ごとに申請書が必要
→ 1つの自治体に1枚ずつ提出します。複数の自治体に寄付した場合は、自治体の数だけ申請書を用意しましょう。 - 6自治体以上に寄付した場合は使えない
→ ワンストップ特例制度は5自治体までが対象です。6つ以上寄付した場合は、確定申告が必要になります。
これらのポイントを守れば、申請はスムーズに完了します。 提出後の控えや送付記録も保管しておくと安心です。
また、「寄附金受領証明書」が後ほど自治体から送付されます。こちらは大切なものなので、必ず保管しておきましょう。確定申告をする際には必ず必要になります。
⏰ 申請期限に間に合わなかった場合はどうする?
ワンストップ特例制度の申請書は、翌年1月10日までに自治体へ届いている必要があります。 もし期限に間に合わなかった場合は、ワンストップ特例制度は利用できません。
その場合は、確定申告でふるさと納税の控除申請を行う必要があります。
「寄附金受領証明書」(申告の際に必要です。)を保管しておき、2月〜3月の確定申告期間に申請しましょう。
「寄附金受領証明書」が見つからない場合は、ポータルサイトのマイページで寄附履歴を確認してみましょう。 一部のサイトでは、証明書の再ダウンロードが可能な場合もあります。 それでも見つからない場合は、寄附先の自治体に問い合わせてみると、代替書類を発行してもらえることがあります。
「寄附金控除に関する証明書」を発行してくれるポータルサイトもあります。(1枚にまとめてくれている)
📝確定申告をする場合の流れ
- 寄付した自治体から「寄附金受領証明書」を受け取る
- 源泉徴収票など他の必要書類を準備
- 税務署またはe-Taxで申告(2月16日〜3月15日)
- 還付金が1〜2ヶ月後に振り込まれる
電子申告(e-Tax)の場合でも、寄付証明書は手元に保管しておきましょう。
後日、税務署から提出を求められる場合があります。
寄付後、自治体が「寄附金受領証明書」を発行・郵送してくれます。
一部ポータルサイトではマイページからPDFでダウンロード可能です。
源泉徴収票、寄附金受領証明書、本人確認、その他必要書類(申告書、振り込み口座情報、控除書類など)を用意します。
確定申告の時期に申告しましょう。
申告したときに記入していた口座に、還付金が振り込まれます。



違いはわかったけど、寄附の申し込みがまだ済んでないよ・・



ではまず寄附サイトで手続きを完了させましょう。
💎 人気ふるさと納税サイトとして、下記のようなサイトがあります。
・楽天ふるさと納税
・
・ふるなび
・Amazonふるさと納税
⏩ あなたに合うサイトを選んで、はじめてみましょう!



寄附の流れをサイト別に確認したい方はこちらから!
▶ 楽天ふるさと納税のやり方
▶ ふるさとチョイスでの申込み手順
まとめ|ふるさと納税後は「申請」を忘れずに!
ふるさと納税の控除を受けるには、必ず「ワンストップ特例」または「確定申告」が必要です。
自分の収入形態・寄付先数などをふまえてどちらにするか決めましょう。
▼ふるさと納税の全体像や控除の仕組みをもう一度確認したい方はこちら👇