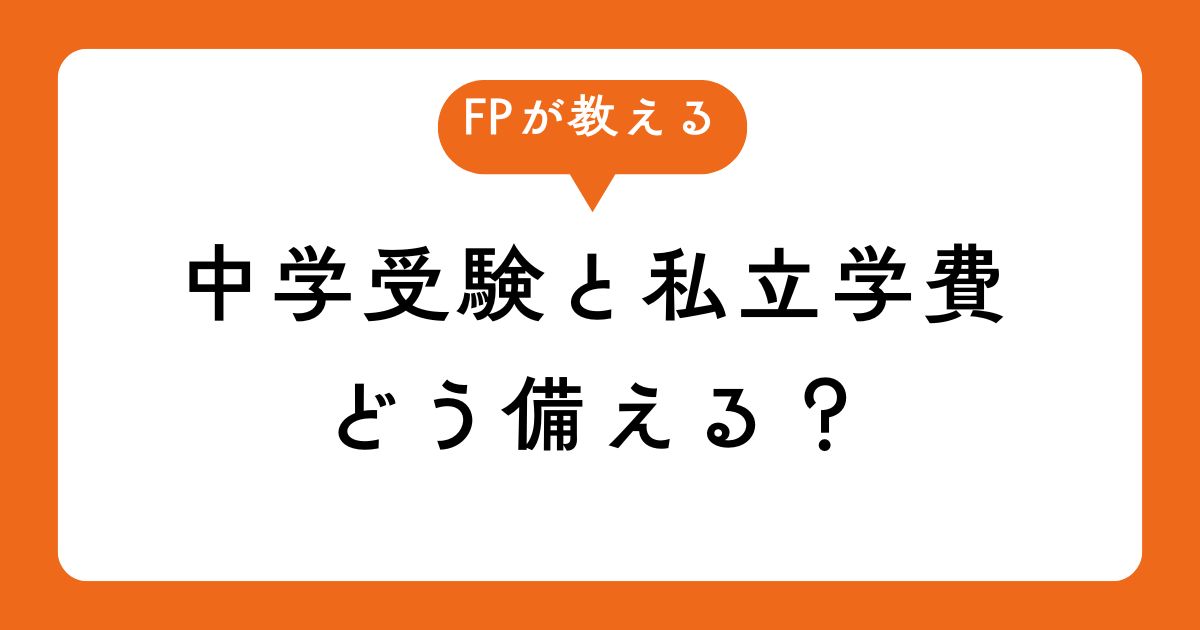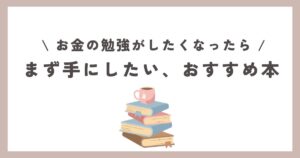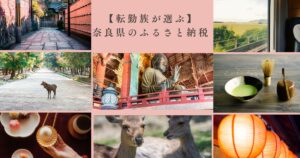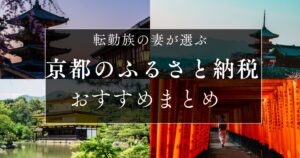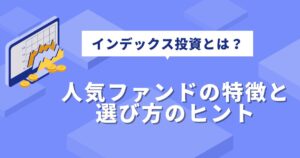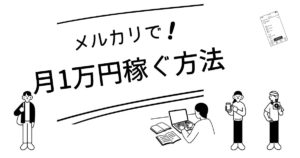中学受験する場合にかかる「塾代」「模試代」・・・
合格したあとの「入学金」…
いつ・どのくらい・どうやって貯めれば良いの?



この記事では、中学受験までに必要な教育費の全体像と、FPとしておすすめの貯め方・備え方をわかりやすくまとめています。
最後まで読むことで、「わが家はいくら必要で、どう準備すれば安心か」がスッキリ見えてくるはずです。
📊 中学受験にかかるお金の全体像
まずは、中学受験に関わる主な費用を整理してみましょう。
「塾代」「模試代」「受験料」「入学金」など、思っている以上に項目が多いです。
🏫 主な費用項目
| 項目 | 年間 or 合計目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 通塾費(小4〜6) | 約150〜250万円(3年間合計) | 大手塾(月3〜5万円)+季節講習・特訓で6年生は一気に増加。 |
| 模試・講習費 | 年5〜15万円 | 模試1回4,000〜6,000円、講習代が加算される。 |
| 教材・テキスト代 | 年2〜5万円 | 塾により異なる。 |
| 入学金・制服・備品 | 合計20〜40万円 | 私立・国立など学校による差が大きい。 |
| 交通費・お弁当代など | 年2〜3万円 | 意外に見落としがちな日々のコスト。 |
※金額は筆者まとめ(首都圏・大手進学塾の一般的水準を参考)
このように、中学受験の3年間で200〜300万円前後がかかるのが平均的なライン。
さらに進学後の学費も続くため、「受験=教育費の山の一つ」として早めに備えることが大切です。
💬 公立か私立か、通塾スタイル(大手塾 or 個別塾)によっても大きく変わります。
さらに、6年生の1年間は授業数や講習が一気に増えるため、「小6だけで100万円を超える」という家庭も少なくありません。
▶ 詳しくはこちら:
👉 【実録】中学受験で実際にかかる費用はいくら?年間・合格までの総額を解説
💡 教育費のピークはいつ?備え方のポイント
教育費は、ある時期に大きくかかります。
つまり“波”のように増えるタイミングがあります。
ここを知っておくと、無理のない貯め方ができます。
📈 教育費の3つのピーク
| 時期 | 主な出費 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1のピーク※ | 中学受験〜入学時 | 塾・受験・入学金など一気に発生 |
| 第2のピーク※ | 高校入学時 | 制服・部活動・通学費などが増加 |
| 第3のピーク | 大学入学時 | 受験料・入学金・下宿費用などが集中 |
▼入学前後の内訳
| 時期 | 主な出費 | 特徴 |
|---|---|---|
| 入学【前年】 | 塾の特訓・模試・直前講習で費用がピーク | 塾代が年間100万円を超えることも |
| 入学【直後】 | 入学金・制服・教材・授業料など一気に支払い | “初年度納入金”で50〜100万円単位の出費も |
このように、受験直前(塾費用)+入学直後(初期費用)が同時に重なることで、 家計のキャッシュフローが大きくマイナスになりやすい時期です。
だからこそ、 「中学受験をするかも」と思ったタイミングで・・というより、もっと前から、子供が小さいときから、 ”先取りライフプランニングからの実行”をすることが重要です。
そうすることで、 入学時の出費も落ち着いて対応でき、 家計全体の見通しもぐっと安定します。
では次に、具体的にどうやって教育費を準備していくかを見ていきましょう。
🎯 教育費の貯め方|まず“見える化”から始めよう



教育費、どうやって貯めたらいいんだろう…
つみたてNISA?学資保険?節約しまくって預金残高増やす?



本当に大切なのは、最初に“自分の家庭のライフプラン”を見える化することです。
お金の不安の正体は「いつまでにいくら必要か分からないこと」だから。見える化さえできれば、「いま何をすればいいか」が明確になります。
📘 ①ライフプランを立てて、教育費を含めた全体像を把握しよう
まずは、現状から、将来の予定までを、少なくとも子供が学校に進学・卒業するまでざっくり書き出しましょう。手書きでもエクセルでもOKです。
- 何年後にどんな進路を考えているか
- どの時期に教育費のピークが来るか
- その時にいくらくらい必要になるのか
- 公的な補助や、貯蓄なども考慮して、いつまでにいくら増やさないといけないのか
現状どうなのかと、上記のようなおおまかな予定を書きだします。
このステップを飛ばしてしまうと、せっかく投資を始めても「どこに、いくら、いつまでに貯めたいのか」が分からず、途中で迷ってしまいます。
💰 ②すぐ使うお金は“現金”で確保
近いうち(約3年以内)に使う予定があるお金は、預金などにおいておきましょう。たとえば入学金や制服代など、時期が決まっている支出などはこれに該当します。
この部分は「貯める」よりも「減らさない」が目的。運用にまわさず、確実に手元に残しておくことを優先します。運用に回さない理由は、短い期間ならば、大幅変動の可能性もあるからです。
📈 ③先まで使う予定のないお金は“じっくり育てる”
7年先~程度の長期に使う予定のお金は、つみたてNISAなどを使ってコツコツ育てていくのが現実的です。(スポット買いでも良いです。どちらが良いのかは個人の性格や考え方にもよるところがあると思っています。)個人的にはインデックスファンドで運用するのが好きで、私自身もインデックスファンドで運用しています。
ただし、これは「万人に一律おすすめ」という意味ではありません。
リスク許容度や目的金額、使うタイミングによって、選ぶ商品や投資額は変わります。
大事なのは、「まずライフプランを立てて、不安を“数字で見える化”する」こと。そのうえで、どのくらいの金額をどんなペースで何で運用していくのか、運用しないのかも含めて決めていきましょう。
教育費の備えは、まず“自分の数字”を出すところから始まります。
👉ライフプランの立て方については、別記事でくわしく解説予定です。(※準備中)
🌍 転勤族家庭の教育費リスクと備え方
転勤族のご家庭では、同じように子育てをしていても「教育費がかさみやすい」と感じることがあります。
これは気のせいではなく、実際に環境の変化が家計に影響しているケースが多いです。
なぜなら転勤の多い家庭では、「いつ・どこで・どんな進路を選ぶのか」が見えづらく、
教育費の見通しが立てにくいのが現実で、引っ越しのたびに環境・学校・塾の費用が変わるため、教育費のブレ幅が大きく、同じ年収でも教育費の負担感がまったく違ってきます。



ここでは、転勤族の家庭が直面しやすい「3つの教育リスク」と、それに対してできる現実的な対策を整理します。
🚚 転勤による3つの“教育費リスク”
そもそも、共働きだった場合、転勤に伴い共働きが継続できなくなり収入が一時的に減る場合があり、家計バランスも崩れやすくなります。ライフプランの見直しも必要です。
① 学校や塾の費用が地域で違う
首都圏や関西圏では、地方よりも塾代・私立校の授業料が高い傾向があります。
転勤によって「教育水準が高いといわれる地域」に移ると、塾代が年間10万円以上増えることも。
② 受験スタイル・制度が違う
地域によっては中学受験文化が根強く、
もともとは考えていなかったけど、転勤先で「うちも受験させるべき?」と迷う家庭も少なくありません。
子どもが影響を受けて、受験すると言う場合も多くあります。
制度の違いからくる準備不足で費用も時間もかかるケースがあります。
③ 子どものメンタルと学習環境
引っ越しのたびに塾を変えたり、学習ペースが乱れたり…。
結果として追加の教材・オンライン学習などの費用が発生するケースも多いです。
🧭 対策①:教育費は“別枠”で意識して管理する
教育費用を生活費と一緒に管理すると、出入りが見えづらくなり、管理が苦手になる方がいます。
その場合は、生活費と教育費を「なんとなく別口座で意識する」だけでもOKです。
月々の収支とは別に、「教育費専用の口座」を作るご家庭も多いです。
筆者自身は、1つの口座でまとめて管理していますが、それでも「教育費」というラベルを意識して可視化するだけで、心理的な備えができます。
つまり大事なのは「分けること」よりも「見える化」することです。
おすすめは、
- 楽天銀行やSBIネット銀行の目的別口座機能
- 毎月自動で一定額を振り分ける設定(例:月2万円)
転勤先の家賃や生活費が変動しても、教育費はまったく影響を受けないようなシステムをつくっておくと安心です。
💹 対策②:まず“ライフプラン”で全体像を見える化する
転勤族の家計は、将来の見通しが立てづらいのが特徴です。 だからこそ、まずはライフプランを立てて「お金の流れ」を見える化することが何より大切。
いつ・どんなタイミングで教育費がかかるのか、何年後にどれだけ貯めたいのかを整理すると、「なんとなく不安」な状態がスッと解消されます。
この“見える化”が、教育費に限らず家計全体の安心につながります。
▶ライフプランの立て方については、今後公開予定です。
🏡 対策③:NISAを活用して“長期の教育費”をじっくり育てる
すぐに使うお金は預金で確保しておくのが基本ですが、10年以上先に使う予定の教育費は、つみたてNISAを利用してコツコツ育てるのもおすすめです。
たとえば「小1→大学入学」までの約15年、毎月2万円をNISAつみたて投資枠で、年利3%の商品で運用すると、約450万円になる試算です。(実際に自分で出した資金は2万円×12カ月×15年=360万円)
全世界株式インデックスなど1本で運用できるファンドを選べば、運用についてなどわからないけどちょっとやってみたいという方にも簡単です。
ライフプランをたててで「必要な金額と時期」が見えていれば、自分がどうすれば良いのかを選びやすくなります。
📊 補助ツールとして、マネーフォワードMEなどの家計簿アプリもおすすめ。
自動連携で、家計の全体像が見やすくなります。
🎓 教育費を貯めるための実践ステップ
教育費の準備は、「なんとなく貯める」では続きません。
FPとしておすすめしたいのは、“自動化”と“見える化”を使った貯め方です。
ここでは、すぐに始められる3ステップを紹介します。
STEP①:【教育費口座を別にしておきたい派の方】目的別口座をつくる(貯める仕組み)
まずは「教育費専用の口座」を分けること。
同じ口座に生活費・貯金・教育費が混ざると、いくら貯まっているのか分からなくなります。
💡おすすめ口座
- 楽天銀行:目的別口座が簡単に作れて、積立も自動化OK
- SBI新生銀行:教育費・旅行費など、目的ごとに名前を付けられる
STEP②:つみたてNISAなどを利用する(増やす仕組み)
中長期で必要なお金は、「つみたてNISA」などを利用すれば、複利の効果も存分に得ながら増やしていくことが可能です。
💹 つみたてNISAの場合
- 月1〜3万円の積立を15年間続けると、運用益非課税で数十万円の差が出ることも。
- 教育費の“中期〜長期資金”にぴったり。
おすすめ証券会社
→ 楽天証券・SBI証券(手数料が安く、初心者にも人気)
▶楽天証券でオルカンを積み立てる具体的な方法についての記事はこちら
STEP③:家計簿で管理(続ける仕組み)
せっかく貯めても、使いすぎたら意味がありません。
教育費を“維持”するには、家計全体を見える化するのがポイント。
💡おすすめアプリ
- マネーフォワードME:銀行・クレカ・証券を自動でまとめて可視化
- Zaim:シンプルで家計簿初心者にも使いやすい
💡その他
手書きのほうが好きなのであれば、手書きの家計簿でも全く問題ありません。
🌈 まとめ:今日からできる第一歩
教育費は「時間」と「仕組み」で勝負が決まります。
転勤やライフイベントが多い家庭ほど、“自動化”でストレスを減らすのがコツ。
- (目的別口座を作って貯める)
- 家計簿で見える化する
- NISAで増やす
この3ステップで、「教育費の不安」を“見通しのある数字”に変えていきましょう。
スポンサーリンク